- Q 現在の研究テーマを分かりやすく教えてください。
↓
-
熱処理は、食品の貯蔵寿命を延ばすために最も広く使用されている技術の1つであり、微生物を死滅させるとともに、食品の風味、食感、外観、および消化率を改善させます。一方で、過度の加熱は、栄養成分の消失や好ましくない食感となって品質が低下する可能性があります。そのため、短時間で均一な温度分布が得られ、なおかつ環境負荷が少ない熱処理方法が望まれます。品質変化は、加工条件に関連して食品中で同時に起こる化学的、生化学的、微生物学的、そして物理的な反応の組み合わせによって生じます。工学的観点からは、これらの変化のメカニズムを実験だけでなく、適切なコンピュータシミュレーションモデルを用いて理解することが重要です。さらにコンピュータシミュレーションを活用することで、熱処理における温度変化を予測し、微生物の死滅の程度や、品質変化などを計算し、最適な熱処理条件を導くことも重要です。この際、食品内部に生じる様々な現象を予測し、現象を制御する術を確立することは社会から強く求められており、食品熱操作工学研究室では、このような課題について取り組んでいます。調理・加工・貯蔵における熱操作を制御し、安全かつ高品質な食品を生産することを目指しています。その手法は、伝熱解析をベースに、デンプン食品から魚肉畜肉に至るまで、対象食品の熱操作による変化の分析までを視野に入れた研究を展開しています。 加熱手法もマイクロ波加熱、IH(Induction Heating、誘導加熱)、ジュール加熱、放射伝熱加熱、過熱水蒸気加熱と多岐に渡り行っています。社会的ニーズに伴い、研究テーマの多くは企業との共同研究へ発展しています。研究室で蓄積されたシミュレーション技術に加え、近年、他分野でも多く利用されているディープラーニングを取り入れた新たな制御法の開発も目指しています。
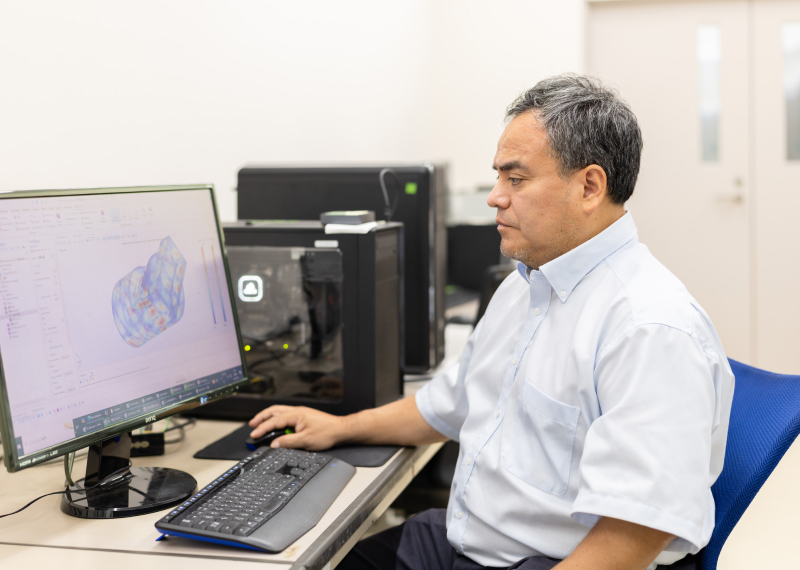
- Q 研究に取り組み始めたきっかけを教えてください。
↓
-
私はペルーの大学を卒業して、シーフード研究センターで働いていました。そこでいろいろな食品が開発されているのを見て、もっと食品工学の勉強をしたいと思い、どこで学べばいいのかということを考えた時に、最初に思い浮かんだのは日本でした。
食品工学の分野では、日本の企業は世界中で一番高い技術を持っていると思います。そこで日本に来て、大学院で勉強をして、そこからそのまま研究室で研究を続けています。 - Q 研究の面白さややりがいを教えてください。
↓
-
例えば、研究テーマが、ある企業の協力のもとにすすむ共同研究であると、そのテーマは、比較的社会ニーズが高いことに対して生産・発信するきっかけとなります。研究により、商品やプロセスがより良くなった時に面白さを感じます。特に、シミュレーションモデルの結果による熱処理のメカニズムと加熱された食品の変化を説明していく過程は、大変面白いと感じています。

- Q その研究の未来を語ってください。
:短期的なもの(1~2年後程度)と長期的なもの(~10年後)
↓
-
食品熱処理機械の近年の技術開発は、処理時間とエネルギー消費を削減し、処理食品の品質保持を向上させることを目的とした、新しいマイクロ波システムや、外部熱処理型と内部熱処理型を含むハイブリッドシステムに重点を置いています。当研究室では、これらの新しいシステムのコンピュータシミュレーションを実施し、その技術的利点を検証するとともに、設計および動作パラメータを改善してプロセスを最適化する研究を行っています。 長期的には、熱システムの複雑さや囲まれているマルチフィジックスの多寡に関係なく、あらゆる種類の熱処理プロセスに対応できるようになると考えています。
現在、コンピュータシミュレーション分野では、作業を簡素化するために多くの仮定を詳述するのが一般的な方法ですが、開発されたモデルの精度と適用性には制限があります。私たちは当研究室に、特に過去10年間で蓄積されたコンピュータシミュレーションの背景を活用し、より柔軟で強力なソフトウェアとハードウェアを採用し、メカニズムモデルとAIモデルを組み合わせることで、あらゆる課題を想定し、プロセスと製品のリアルタイムでの最適化を重視する食品産業分野の要件に対応できるようになると信じています。 - Q 研究は、SDGsのどの目標に貢献できますか。
↓
-
調理・加工工程における熱媒体の挙動、素材の伝熱・物質移動・反応を予測するためのモデルが提供されることで、高品質な調理ができる加熱機器の設計や制御に役立ち、また必要十分な加熱処理を行うことで調理・加工における省エネルギー化も可能になります。したがって、食品熱操作工学研究室は、環境負荷を低減する食品製造技術、加熱調理の最適化、食品熱処理技術の設計という3つの分野に注力し、以下のSDGsへの貢献を目指しています。
「目標 9: 産業と技術革新の基盤をつくろう」
「目標13: 気候変動に具体的な対策を」 - Q 東京海洋大学で研究する良さはどんなところですか。
↓
- 東京海洋大学の食品熱操作工学研究室は工学系の分野ではとてもグローバルな開かれた環境があります。研究室の歴代の先生や先輩方が残してくださった様々な技術やノウハウのおかげで、非常に高い研究レベルを維持しています。私自身も現在は熱処理分野の中でより緻密な研究やシミュレーションモデルを日々研究し、次世代につないでいきたいと思っています。学生たちも、日本や海外の食品会社へ就職するものも多く、自身の仕事にこのバックグラウンドの一部を活用しています。
- Q 研究を行う上で大切にしていることやポリシーを教えてください。
↓
- 「研究能力を育てる」 。当研究室には教員が2名おり、指導教員として直接学生を指導しています。学生たちがいつでもあらゆるトピックについて相談できるよう、柔軟に対応しています。研究テーマも、一人ひとり個別のテーマを決めて研究を進めます。得られた成果は学生の研究業績となり第一著者として論文を書きます。このように、一対一で、学生のペースで研究を進めるというのが、ひとつの特徴です。 研究に関連する論文の紹介や、各自の研究の進捗状況についての報告会(ゼミ)の実施。また、個々の研究テーマに関しては、定期的な個別ディスカッションを行い、理解と問題点をつめていきます。 卒論テーマも自分自身の研究と捉え、学生に自分で計画を立て実行するよう指導しています。
- Q 研究に疲れた時のリフレッシュ方法を教えてください。
↓
- 海洋大のキャンパスにはとてもたくさんの緑があります。植物を見ながら散歩すると、リフレッシュできます。学生とキャッチボールやバレーボールをする時もあります。
- Q 研究者を目指す人へのメッセージをお願いします。
↓
- 私の研究室では物理学や化学、工学など複数の視点から食品の加熱を探っているので、興味を持ってもらえるとうれしいです。もしあなたが食品科学を学びたければ、高校で物理や化学や数学をきちんと勉強しておきましょう。「本当に役に立つのかな」と疑問を感じることもあるかもしれませんが、例えば食品の変化を予測するモデルは、物理や化学や数学などを組み合わせて作られています。高校で学んだ内容は大学できっと役立ちますし、社会で活用できる考え方も身につきますから、将来の夢にむかって、学んでほしいです。





