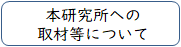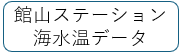館山ステーション水温データSERVICE&PRODUCTS
概要
 20XX年から館山ステーションの取水口でモニタリングされている海水温データを提供します。
20XX年から館山ステーションの取水口でモニタリングされている海水温データを提供します。(台風等による停電、改修工事等でデータに欠失時期があります。
ご希望される方は、ke-ken★o.kaiyodai.ac.jp(研究企画係)までメールにてご連絡ください。(★は@(半角)に置き換えてください)
測定場所所在地・マップ
住所〒294-0308
千葉県館山市坂田670地先(館山湾内・洲崎灯台から1km)
地図
施設周辺案内
本ステーションは房総半島南西端近くに位置し、東京湾口・館山湾に北面し、対岸には三浦半島を望む。沿岸は黒潮の影響が強く、水温は冬期でも12℃以上、夏期には25〜27℃位である。気候も温暖であるが、冬期には洋上から北西風が直接当たるため、強風と波浪の影響を受け易い。
海岸構造は、東側の館山湾は砂浜域であるが、西側にゆくに従い岩礁が出現し、西端の洲崎から半島先端を回った西川名・伊豆にかけて岩礁が連なる。地先海岸は岩礁帯と砂礫帯が交互に連なり、岩礁帯は比較的遠浅で距岸200m位から沖は砂礫底に変化する。潮間帯には多様な生物群集がみられ、岩礁に固着する二枚貝類、ヒザラガイ、カサガイ、フジツボ類および海藻類などの帯状分布が観察される。浅海域ではアワビ、トコブシ、サザエ、アオリイカ、マダコ、イセエビ等重要磯根資源に富むと共に、ホンダワラ類、ヒジキ、ワカメ、アラメ、ハバノリ、テングサ、トサカノリ等有用海藻類も豊富である。
その他天然岩礁や人工漁礁に蝟集する底生動物・沿岸性魚類も南方系の種類から内湾性の種類も混ざり、多様性に富んでいる。さらに沖の岩礁および砂礫底にはウミトサカ、ウミエラ、ヤギ類、イソギンチャク類、イシサンゴ類等の刺胞植物を多産し、特に造礁性のイシサンゴ類は館山湾から坂田沿岸にかけて23種類の生息が確認され、館山湾は北限のサンゴ生息地として注目された。
(平成5〜6年にかけて、更に北に位置する鋸南町沖において礁を形成するほどのイシサンゴ類のコロニーが発見され、また分布の北限が塗りかえられている)
写真